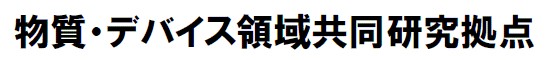研究テーマ(A) 【グリーンナノサイエンス・デバイス研究開発】
1) 量子もつれ光を用いた、新しい物質・材料・生命研究の創成
- [研究概要]
- 量子もつれ光とは、構成する光子間に強い相関をもつ、通常のレーザー光線などとは全くことなる光の状態である。量子もつれ光の研究は、量子情報通信処理の発展の中で近年精力的に進められてきた。その発展に伴い、量子暗号や量子コンピュータなどの次世代情報通信処理だけでなく、レーザー光などの従来の光では実現不可能な「光と物質との相互作用」や、さらにはその限界を超えた、感度の高い光計測技術などの可能性が、最近理論的に指摘されている。
本研究は、「光子一粒が制御された光」という新しい光の状態を利用する、まったく新しい物質・材料・生命研究を、将来的な物質・デバイス領域における新しい学術領域の創出を視野に入れて進めようとするものである。たとえば、「物質・材料における多光子プロセスの、不確定性原理による限界を超えた高い時間分解能(~fs)での観察」、「量子もつれ光を用いた、生命現象の超高感度観測技術の開発」などの実現が期待される。
- [オーガナイザー]
- 竹内 繁樹 (北海道大学電子科学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 笹木 敬司 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 居城 邦治 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 根本 知己 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 田中 秀和 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 横山 士吉 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 4件程度
2) 革新的エネルギー機能を発現する界面ナノ物質の創製
- [研究概要]
- 従来の材料科学の常識外にある物質機能発現を目指した新しいアプローチを探究する。例えば、絶縁体をリチウム電極(LiFePO4の例)や超伝導体にする革新的材料設計の基盤構築を行う。低次元性や非対称性を有する新奇な界面物質合成法および表面界面特有の量子現象やエネルギー物性の探索的研究を行う。
① 新奇な界面物質合成法
表面界面から構成されバルクにはない革新的エネルギー機能を有する低次元・非平衡・非対称物質合成法の開発を行う。「ナノ粒子(メカノケミカル反応)」、「グラフェン(超臨界流体合成)」、「非対称物質(単結晶合成)」、「トポロジカル絶縁体(薄膜合成)」、従来にない概念の新材料の革新的合成法を開拓する。例として可変性や非対称性の概念を有する新しいナノマテリアルを創製する。
② 革新的エネルギー機能の探索
「電気二重層」、「超伝導」、「イオン伝導性」、「磁性」、「スピン流生成」、特に電子・イオンの新しいエネルギー輸送・貯蔵原理の探索を行い、電力送電・電力貯蔵・エネルギー変換技術の革新的デバイス材料創製の基盤を築くことを目的とする。工学的応用としては超伝導デバイスやスピントロニクスデバイス、キャパシタ・リチウム電池を想定する。
- [オーガナイザー]
- 本間 格 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 加納 純也 (東北大学多元物質科学研究所准教授)
- 齋藤 文良 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- 張 其 武 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 笘居 高明 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 宇根本 篤 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 安藤 陽一 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 瀬川 耕司 (大阪大学産業科学研究所准教授)
- 尹 聖昊 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 4件程度
3) 環境適応型エネルギーデバイスの技術革新へ向けたマテリアルサイエンス
- [研究概要]
- 本研究では、環境適応型エネルギーデバイスの技術革新を目指し、従来にない革新的な新規材料の創生と技術基盤の構築を行う。エネルギーデバイスとして、特に電池、キャパシタを対象とする。化学エネルギーから発電を行う燃料電池、太陽光から発電を行う太陽電池、蓄電を行う2次電池及びキャパシタ、それぞれの技術革新には、従来にない新しいアイデアによる機能性材料が必要不可欠である。出口を見据えたデバイス技術開発と様々なアイデアによる材料開発を統合し、共同研究の枠組みを有効に生かし、環境適応型エネルギーデバイスのためのマテリアルサイエンス基盤を構築する。
- [オーガナイザー]
- 山口 猛央 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 穐田 宗隆 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 福島 孝典 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 山元 公寿 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 阿尻 雅文 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 4件程度
4) 新物質・ナノテクノロジーを利用した次世代省エネルギーナノデバイス開発研究
- [研究概要]
- 次世代省エネルギーエレクトロニクスの実現に向けて、従来のSiを凌駕する機能を発現する、新規物質およびそのナノ構造を活用した新機能デバイスの創製に関する研究を行う。
対象分野として、例えばスピンエレクトニクス・デバイス、分子エレクトロニクス・デバイス、ナノカーボンエレクトロニクス・デバイスなどが挙げられる。
重点課題目標に資する、ナノ構造(人工ヘテロ構造、超微細加工構造、ナノチューブ・ナノ粒子合成など)形成による新規な優れた機能の発現と、その省エネルギーナノデバイスへの適用に関する共同研究を行う。
応募研究者野のアイデア・研究成果と拠点研究者の研究成果・設備の相乗効果による、新たな研究領域の形成につながる研究提案を募集する。
- [オーガナイザー]
- 田中 秀和 (大阪大学産業科学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 朝日 一 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 松本 和彦 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 竹谷 純一 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 鷲尾 隆 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 安藤 陽一 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 安蘇 芳雄 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 小口 多美夫(大阪大学産業科学研究所教授)
- 末宗 幾夫 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 中川 勝 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- 進藤 大輔 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 4件程度
5) 新規電子系化合物の合成と光・電子機能開拓
- [研究概要]
- 得意な電子構造を有する有機化合物は光エレクトロニクス材料として新機能の発現や無機・半導体材料を超える高い光・電子特性を持つことで期待されている。一方、これらの新規化合物の合成には卓越した有機合成技術が必要であることから、有機光エレクトロニクス分野の発展には、合成化学分野と密接に連携した同研究を実施することが重要である。
本重点課題では、「新規電子系化合物の合成と新機能の発現」を焦点とし、π電子系化合物やSi系電子化合物の新規開発と高度な物性計測を究連携することによって、有機系光電子機能の開拓に関する先端的な研究を推進する。
π電子系ヘテロ化合物の触媒的不斉合成、Si系電子化合物の新規合成法の開拓、π電子縮合系共役分子の光電子機能、および光電子機能評価を中心とした共同研究を実施し、各テーマ間の連携研究によって新規電子系化合物の合成から機能評価に関する基盤研究を進める。本共同研究によって高度な有機合成技術によって創出される新規電子系化合物の開拓と有機系光エレクトロニクスへの応用につながる材料基盤技術の拡充を目指す。
- [オーガナイザー]
- 横山 士吉 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 友岡 克彦 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- 永島 英夫 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- 新名主 輝男(九州大学先導物質化学研究所教授)
- 小坂田 耕太郎(東京工業大学資源化学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 3件程度
このページの先頭へ
特定研究課題の公募に戻る