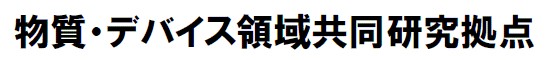研究テーマ(B) 【バイオメディカルナノサイエンス・デバイス研究開発】
1) 生体ナノシステムの動作原理の理解に基づいた新規医療材料・バイオナノデバイスの創成
- [研究概要]
- 生命現象の本質の一つとして、"数個から数10個程度"の少数の要素分子から構成されるナノシステムが"協同的"に動作することが挙げられる。これまで、1分子計測を中心とした"単分子"の素過程を観察した例は数多く報告されているものの、"少数分子間"で生まれる協同性の素過程を生きた細胞内において解析した報告は"皆無"であり、少数の要素分子が如何にして極めて高い協同性を生み出すのかについては全く分かっていない。少数分子が協同的に反応することで、出力の安定化に寄与する一方、分子の少数性に起因する不安定な出力も起こり得る。この反応の曖昧さが、ひいては、階層を越えたマクロな生命システムの動作安定性と一部の動作不安定性に結びつく可能性があり、生命の動作原理を理解する上で、極めて重要な観点といえる。しかしながら、細胞内における少数の分子反応を扱う理論が未整備であったことに加え、少数分子の細胞内挙動を操作し計測する技術も無かったため、これまでほとんどアプローチされてこなかった。
そこで本研究課題では、このような少数分子からなる生体システムを実験に供し、理論を構築するために、①子数の計測と制御を可能にする基盤技術開発研究、②モデル生命現象に①で開発した技術で切り込む解析研究、③得られたデータをもとに、1分子系と多分子系のギャップを埋める少数分子系理論の構築、ならびにその理論を再構成系で検証する研究を推進する。
本研究課題では、顕微光学、MEMS工学、蛍光物理化学、合成有機化学、タンパク質工学、細胞生物学、システム生物学、数理科学の諸分野を融合し、技術開発系と実験系、理論系の専門家が手を組み、従来とは異なる視点で生命現象にアプローチする。とくに、少数の生体分子からなる化学反応システムにおける分子間の協同性、超コヒーレンス、自己組織化、ポアソン性、エルゴード性、多階層間相互作用などの観点からのアプローチを進める。本研究課題で扱う生命現象は真核生物、原核生物を問わずあらゆる生物で見出される現象であることから、生命現象一般を説明しうる統一的原理の提出を目指す。
- [オーガナイザー]
- 永井 健治 (北海道大学電子科学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 小松崎 民樹 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 玉置 信之 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 西野 吉則 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 石島 秋彦 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- 久堀 徹 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 中谷 和彦 (大阪大学産業科学研究所)
- [採択予定課題件数]
- 4件程度
2) 生体分子素子の分子レベルでの機能および機能制御原理解明と環境負荷の少ない次世代機能材料としての展開
- [研究概要]
- 生命現象において、協同的に極めて多彩で優れた機能を発現している生体分子素子の分子レベルでの機能解明、ならびにその機能動作・制御原理の検討、さらにこれら基礎的知見に基づく新規機能材料創製が、自然負荷の少ない次世代機能材料系構築の点からも注目され、現在最も重要な研究課題の一つとなっている。本目的を達成するには、タンパク質や核酸そして糖類など、生体分子素子機能を1分子レベルで観察・計測し、その機能制御原理を解明する必要があり、最先端の計測法開発が求められる。さらに分子レベルで解明された機能ならびにその制御原理に関する情報に基づき、生体素子の機能材料としての応用展開するためには、生体素子を対象とした高度な化学修飾法の開発や、その特性解明法の構築が必要不可欠である。
本研究課題では、先端的高感度計測システムを用いた生体素子の機能・制御原理の解明、さらに生体素子に基づく新規機能性材料創製に関する先導的研究を以下の2つのテーマに大別し推進する。
① 新規ナノバイオ計測システムの開発
従来の分割型フォトダイオードによる計測手段だけでなく、高速度カメラを用いた高空間時間分解能を有し、さらに複数のターゲットを同時に計測できるシステムの開発を行う。さらに、その解析には膨大な時間がかかることからデータ解析アルゴリズムの開発も同時に行う。
② 生体素子を活用した新奇機能材料の創製
近年ナノバイオ機能材料が注目され、多くの研究が報告されている。しかし、多くの系は生体内で高度な機能を発現しているタンパク質や核酸、そして多糖類など複雑な生体高分子複合系を対象としていながら、化学合成可能な比較的単純な化合物をモデルとして用いた、所謂ボトムアップ型手法が用いられてきた。しかし、これまでの研究成果からこのような方法論のみでは生体機能素子のように多彩で優れた機能を有する材料創製を実現することが厳しい事が明らかとなっている。このような背景を踏まえ、本研究では生体素子の分子レベルでの機能解明などの知見を踏まえ、タンパク質や核酸など生体高分子を機能材料創製のターゲットとして捉え、これらの分子に対し直接化学修飾などを施すことにより新奇で多彩な機能を有する材料創製を実現するため先導的研究を推進する。
- [オーガナイザー]
- 和田 健彦 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 荒木 保幸 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 坂本 清志 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 井上 裕一 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 福岡 創 (東北大学多元物質科学研究所助教)
- 居城 邦治 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 丸山 厚 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 5件程度
3) 生体機能物質の機能解析と光制御
- [研究概要]
- 生体機能は、神経伝達物質やアミノ酸、ヌクレオチドの様な低分子やタンパク質・核酸の様な高分子など様々な分子によって制御されており、その機能の解明と制御は化学が生命科学に翼を広げる上で極めて重要なトピックスである。本共同研究では資源化学研究所のレーザー分光及び生化学グループが対応教員となり、レーザーイオン化分光、二光子顕微鏡、タンパク質の精密ハンドリングなどレーザー分光と生化学の先端的な技術と研究力を生かし、低分子側とタンパク質側の両面から分子認識のメカニズムの解明を行う。
- [オーガナイザー]
- 藤井 正明 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 久堀 徹 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 田中 寛 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 酒井 誠 (東京工業大学資源化学研究所教授)
- 太田 信廣 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 松田 知己 (北海道大学電子科学研究所助教)
- [採択予定課題件数]
- 3件程度
4) バイオメディカルデバイス・システム創製に資する要素技術の開発研究
- [研究概要]
- 本重点研究課題では、生命機能解明技術、物質合成技術、情報処理技術を駆使することにより、世界をリードする医療材料・デバイス・システムを創製すべく、その実現に必要な幾つかの要素技術の開発研究を行う。下記のようなライフイノベーションに資する要素技術に関連した先端的な研究を公募し、採択課題をネットワーク拠点との共同研究として推進する。
具体的には、①標的能を有するナノキャリアーの開発とこれを用いて核酸医薬を含むさまざまな薬剤を生体内の特定の臓器や組織、あるいは細胞にピンポイントで送達する技術の確立、②生体内脂質動態に関わる脂質輸送デバイスの同定とその作動原理の解明を基盤とした、脂質関連疾病に対する分子標的医薬の創出、③オンサイトでの確定遺伝子診断を実現するPCRの迅速化技術の確立とPCR結果の簡便なモニタリングシステムの構築によるヘアピンプライマーPCR法の実用化、④臨床検体からのウイルス粒子やゲノムの分画・濃縮、ウイルスゲノムの高感度可視化ツールの開発を基盤とするウイルスゲノムの目視診断技術の確立、⑤カプセル内視鏡による読影診断支援技術の高度化に必須な、病変を含む微細構造の三次元構造復元、病変鮮鋭化、病変追跡、腸管モザイク処理等のイメージ解析ツールの創出、⑥看護業務手順やリスクマネージメントマニュアルなどの整合性化、看護技術の蓄積、さらに病院間のガイドラインの相互運用性の確保など、安心・安全医療に資する医療ガイドラインのオントロジー工学技術による創出などである。
- [オーガナイザー]
- 加藤 修雄 (大阪大学産業科学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 谷澤 克行 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 山口 明人 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 中谷 和彦 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 八木 康史 (大阪大学産業科学研究所教授)
- 溝口 理一郎(大阪大学産業科学研究所教授)
- 根本 知己 (北海道大学電子科学研究所教授)
- 永次 史 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- 三治 敬信 (東京工業大学資源化学研究所特任准教授)
- 狩野 有宏 (九州大学先導物質化学研究所准教授)
- [採択予定課題件数]
- 6件程度
5) バイオ分子集積体・バイオ界面の機能的構築のための分子分解能解析
- [研究概要]
- 一分子レベルでの観察および計測技術は、先端的顕微鏡技術と超感度CCDカメラの発達によってその解析対象の範囲を拡大し、様々な分子集積体や界面材料の設計における分子分解能での基礎的知見を与えつつある。このような分子分解能の科学はナノバイオサイエンスの発展のみならず、工学材料設計との密接な連携によって今後の分子基礎科学と新機能性材料の構築の分野に対しても極めて重要な貢献をなすものと期待される。本重点課題では、この「分子分解能の科学」を焦点とし、バイオ分子集積体およびバイオ界面の設計で先端的な研究を推進する。
マイクロ流路を利用したDNA・リガンド相互作用の一分子計測、水溶液中での分子超を認識して形成される会合体の構造解析、および人工膜系への細胞膜シグナル伝達経路構築とその機能評価を中心とした共同研究を実施し、各テーマ間の連携研究を開拓する。本共同研究によって一分子観察・計測に基づく分子分解能解析技術を駆使し、DNA/リガンド複合体系、水分子集合体、人工膜系などの機能的構築と分子基礎科学の拡充を目指す。
- [オーガナイザー]
- 木戸秋 悟 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- [共同研究教員]
- 丸山 厚 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- 高原 淳 (九州大学先導物質化学研究所教授)
- 金原 数 (東北大学多元物質科学研究所教授)
- [採択予定課題件数]
- 3件程度
このページの先頭へ
特定研究課題の公募に戻る