イベントレポート
年度

施設見学報告(1月~3月)

日本機械工業連合会ご一行が来所されました。

施設見学報告(11月~12月)

「産研安全講習会」を開催しました。
令和6年12月4日(水)、産業科学研究所管理棟1階講堂にて、研究者および学生を対象に「産研安全講習会」を開催しました。当日は、黒田俊一所長からの挨拶の後、本学安全衛生管理部の山本仁教授に、「化学物質の ...

第80回産研学術講演会を開催しました。
学術講演会が2024年11月22日(金)に開催されました。「持続可能な産業科学」をテーマに、京都大学生存圏研究所の名誉教授であり特任教授の矢野浩之氏による学外講演「木材の魅力 ~楽器から自動車まで~」 ...

Artec Malaysiaの学生さんが来所されました!
9月24日、国際ロボット競技会に参加するために来日したArtec Malaysiaの学生さんたちが、産研を訪問しました。彼らは、小中学生向けの大会に向けた準備とともに、私たちの研究や技術に触れる機会を ...

Spectris社(英国)ご一行が来所されました
2024年10月8日(火)、坂本研究室にグローバル企業体のSpectris社(英国)より表敬訪問がありました。今回来訪してくださったのは、マルバーン・パナリティカル事業部からMark会長、Spectr ...

グローニンゲン大学長ご一行が来所されました。
2024年10月10日(木)、オランダのグローニンゲン大学より学長をはじめとする代表メンバー計10名が、大阪大学産業科学研究所を訪問しました。 大阪大学と交流協定を締結しているオランダのグローニン ...

中国科学技術大学から大学院生が産研を訪問しました。

SANKENものづくり教室2024を開催しました。

開成学園の学生さんたちが、産研を訪問しまし た。

西大和学園、奈良女子大学附属中等教育学校の学生さんがラボステイを行いました。

中国の清華大学の学生さんが産研を訪問しました。

中国の浙江大学が産研を訪問されました。

六甲学院中学校の生徒さんが産研を訪問しました。
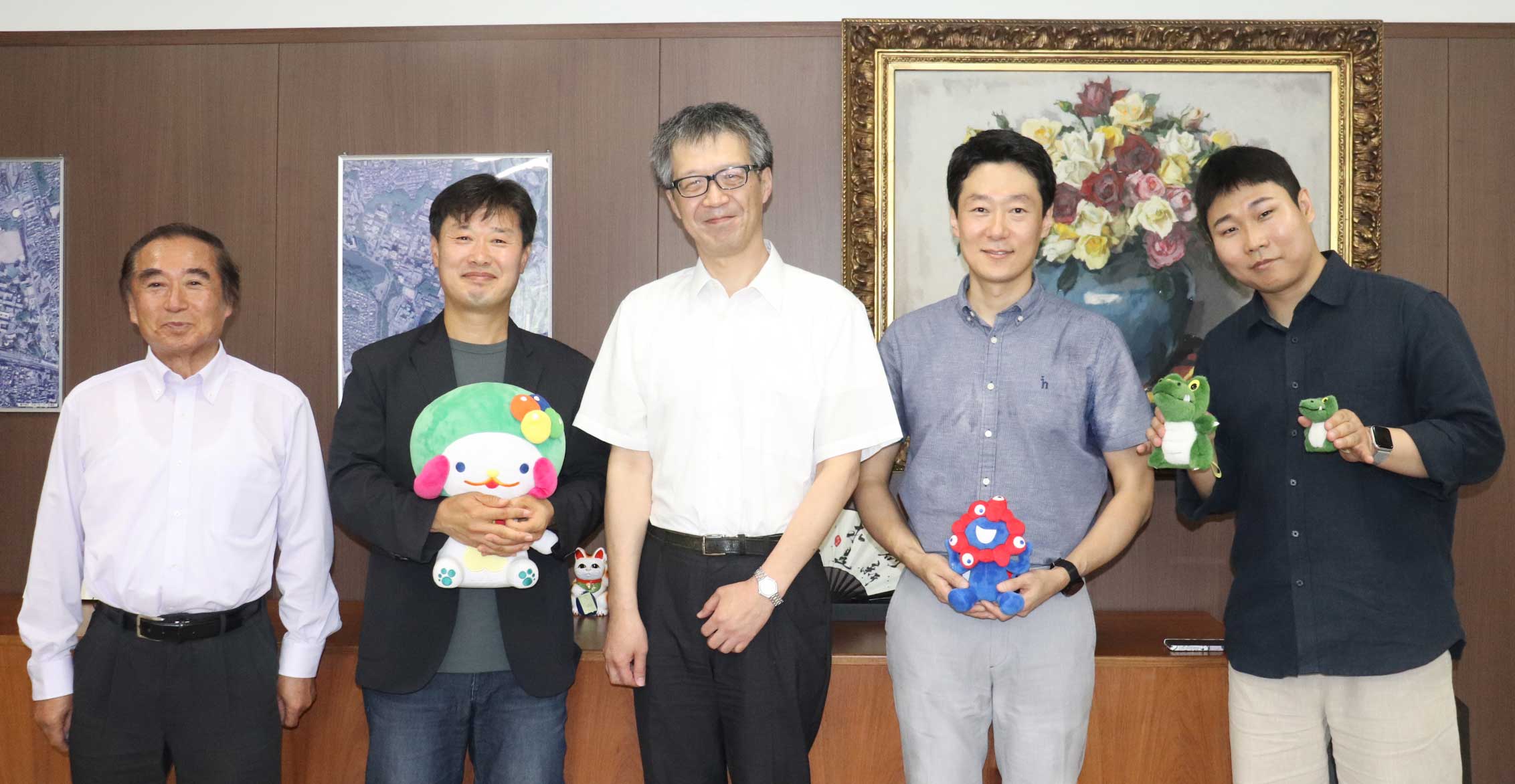
韓国(KETI)の研究者が産研を訪問されました。

四天王寺高等学校の女子生徒たちが施設見学に来訪しました。

今年もSANKENいちょう祭を開催しました!

立命館高等学校および韓国Korea Science Academy of KAIST(KSA)の生徒が産研を来訪しました。

